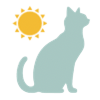ふと
「うちの子、そろそろシニアかも?」
と思う瞬間ってありますよね。
そんな気づきは、とても大事なサインです。

猫って何歳からシニアなの?
うちの子はもうシニアなのかな?

今回は、このような疑問について一緒に解決していきましょう。
猫は7歳を過ぎたころからシニア期を迎え、少しずつ体や心に変化が現れます。
「まだ元気だから大丈夫」
と思っていても、老化は静かに進んでいます。
大切なのは、その“変化の瞬間”に気づいてあげること。
本記事では猫のシニア期の目安と、飼い主さんが知っておきたい7つの老いのサインをご紹介します。
目次
シニア猫って何歳から?猫の年齢とシニア期の目安

猫は人よりもずっと早く年を取ります。
1歳が人の約15歳に相当し、2歳が24歳、その後は1年におよそ4歳ずつ年を重ねると考えられています。
そして、7歳を過ぎる頃には約44歳、人間でいう中年期に入ります。
ちょうど健康管理を意識し始める時期ですよね。
*猫の年齢に関する考え方は諸説あります。
猫の場合、7歳から15歳までをシニア期、15歳以上をハイシニア期とする考え方が多いようです。
ただし、生活環境や体質によって老化の進み方には個体差があります。
食事の内容や運動量、ストレスの少なさなどが老化のスピードを左右します。
そのため、年齢の数字だけで判断するのではなく、行動や体調の変化にも目を向けることが大切です。
次に紹介する「7つの瞬間」は、その変化にいち早く気づくための目安になります。
シニア猫って何歳から?気づいてあげたい7つの老いのサイン

①ごはんを残すようになったとき
食欲が落ちてきたら、体のどこかに不調を感じているかもしれません。
口腔内の痛みや消化力の低下、腎臓の働きの変化などが考えられます
- 食べるスピードが遅くなった
- 好きだったごはんを残す
- 飲む水の量が変わった
こうした小さな違いは、老化のはじまりのサインです。
無理に食べさせず、やわらかく温かいごはんに変えるなど、少しの工夫で改善できる場合もあります。
②毛づやが落ちたと感じたとき
毛がパサついたり、ツヤがなくなったりするのは、代謝の変化や栄養不足の合図です。
毛づくろいをする回数が減っている可能性も。
- 毛がごわつく フケが増えた
- 毛づくろいを途中でやめてしまう
- 抜け毛が増えた
ブラッシングを優しくしてあげると、血行もよくなり健康維持にもつながります。
毛並みの変化は、体調の鏡です。
③高いところに登らなくなったとき
昔は軽々と棚の上に飛び乗っていたのに、最近は登らなくなった――。
それは、足腰の筋力が落ちてきたサインかもしれません。
- ソファやベッドに上がるのをためらう
- 着地の音が大きくなった
- 以前よりも寝ていることが増えた
このような様子が見られたら、段差の少ない環境を整えましょう。
スロープを置くなど、体に負担をかけない工夫が必要です。
④トイレの失敗が増えたとき
ハイシニア期になると、筋力の低下や関節の痛みでトイレまで行くのが難しくなることがあります。
また、泌尿器系の病気が隠れている場合もあるので、注意が必要です。
- トイレの入口を低くする
- 複数の場所にトイレを置く
- 排尿や便の回数・量を記録しておく
叱るのではなく、まず環境と健康の見直しをしてあげましょう。
⑤よく寝るようになったとき
睡眠時間が長くなるのは、体力の低下や代謝の変化が原因です。
一日のほとんどを寝て過ごすことも珍しくありません。
ただし、寝方にも注意が必要です
- 呼びかけてもすぐに反応しない
- いつもと違う場所で寝ている
- 眠りが浅く落ち着かない
これらが続く場合は、体調不良の可能性があります。

我が家の猫(10歳男の子)も、いつもと違う場所で寝ているなと思っていたら体調を崩したことがあります。
安心して眠れる環境を整え、異変を見逃さないようにしましょう。
⑥甘え方が変わったとき
猫はシニア期に入ると、心にも変化が生まれます。
昔より甘えん坊になる子もいれば、一人の時間を好むようになる子もいます。
どちらの場合も「変わった」と感じたときがサインです。
- 鳴く回数が増えた
- 抱っこを嫌がるようになった
- 飼い主のそばを離れない
猫の気持ちは日々変化します。
無理に合わせようとせず、その子のペースに寄り添うことが大切です。
⑦病院に行く回数が増えたとき
年齢を重ねると、どうしても通院の回数が増えてきます。
検査や診察を通して、健康状態をこまめに確認することが長生きの秘訣です。
- 年に1~2回は健康診断を受ける
- 小さな異変でも早めに相談する
- 病気の早期発見を意識する
「年齢的に仕方ないのかな?」と思わず、早めの受診を心がけましょう。
それが、猫の「今」を守る一番の方法です。
まとめ:変化の瞬間に気づくことが長生きの鍵

シニア猫の変化は、ある日突然ではなく、ゆっくり進んでいきます。
だからこそ、日常の中の7つの瞬間に気づくことが何より大切です。
- ごはんを残したとき
- 毛づやが落ちたとき
- 高い場所に登らなくなったとき
- トイレを失敗したとき
- よく寝るようになったとき
- 甘え方が変わったとき
- 病院に行くことが増えたとき
これらの変化を優しく受け止め、生活を少しずつ整えてあげましょう。
その積み重ねが、飼い主さんと愛猫の幸せな時間を長くしてくれます。